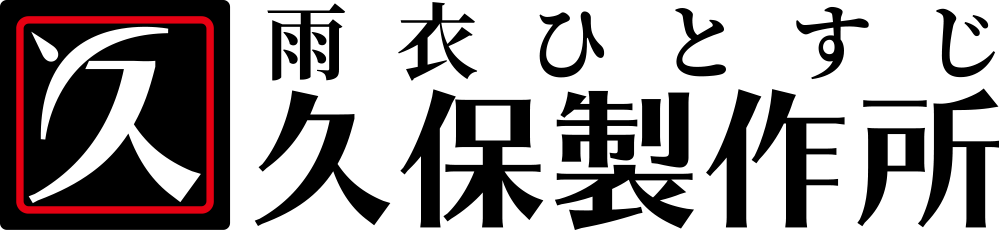皆さま、こんにちは。今月は出だしからインフルエンザにかかってしまいました。
年末の忘年会に参加して、3日目の大晦日の夜から何となく具合が悪くなり、熱を測ると38.5度。
人生初、元旦に病院へ行ってきました。
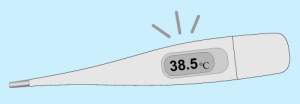
新聞で年末年始の当番医を探し、事前に電話したところ、もしインフルエンザなら今は吸入用の薬しか在庫がない、飲み薬がいいなら隣の海南市の調剤薬局にある、とのことでした。
タミフル等インフルエンザ治療薬が不足していて、一部供給を一時停止しているというのは、テレビや新聞等を見て知っていました。
が、その他の薬についてはよく知らず、その時は吸入タイプの薬?と言われてもピンときませんでした。
人生初、元旦に病院へ
早速、車で5分もかからない紀美野町内の病院へ行ってきました。数名の患者さんがいらっしゃいましたが、それほど待たず検査へ。
5分後、インフルエンザと診断されました。11月にインフルエンザ予防接種をしたのですが・・・。
それから車で15分程の所にある海南市の調剤薬局へ行き、飲み薬を貰ってきました。ゾルフールという薬でした。
その後、新聞でインフルエンザ治療薬がいろいろあると知りました。吸入用の薬はイナビル、一時供給を停止していたのはタミフルの後発薬(ジェネリック医薬品)でした。
薬が効いたのか、翌日には37度近くまで熱が下がり、3日後にはほぼ元通り元気になりました。
具合が悪かったのは病院に行く前日の大晦日の夜、元旦、二日ぐらいでした。幸い母にもうつらず良かったです。
インフルエンザは潜伏期間が1~3日と短いのが特長だと聞いてはいましたが、実際インフルエンザになってみてよくわかりました。
29日 忘年会に参加
30日 忘年会に参加した友人からインフルエンザにかかったと連絡あり
31日 夜から発熱(38.5度)
1日 病院でインフルエンザと診断される、薬(ゾルフール)を飲む
2日 熱が37度まで下がる
3日 食欲が戻る
4日 ほぼ元どおり元気になる
検査にもタイミングがあった
今回、インフルエンザの検査にはタイミングがあると知りました。症状が出始めてから12時間~48時間以内が検査のタイミングだそうです。
ウイルスが検査に必要な量まで増えるのに12時間程かかり、48時間以降はウイルス排出量が減るため、陰性となる可能性があるそうです。
また抗インフルエンザ薬は、症状が出始めてから48時間以内に飲むと効果を発揮するそうです。
私は大晦日の夜に熱がでて、元旦に病院で検査しました。12時間経っていましたから、検査のタイミングも薬を飲むタイミングも、ちょうどよかったようです。
インフルエンザは辛い・・・
私の場合病院での検査も、薬の受取りも、治りも、全てスムーズでしたが、ある友人は、病院へ行って診察前の検査だけで3時間もかかったそうです。具合の悪い時に、本当に気の毒です。
私は運転して病院と薬局へ行くことができましたが、熱が出て具合が悪くて病院にも行けず、寝込んだ人もたくさんいると思います。
東京近郊にいる友人の話ですが、ご主人が突然頭痛と悪寒がして、風邪だと思い病院に行ったところ、検温して熱がないからインフルエンザではないだろうと診断され、風邪薬を貰って帰宅。
翌日には友人の具合が悪くなり(うつった)、熱を測ると39度。そのうちご主人も熱がでて、二人で数日寝込んだそうです。3日もお風呂に入れなかったと言っていました。
風邪の症状で熱がある場合、都会では発熱外来に予約してから行くようになってるそうですが、熱がでて具合が悪くなると、予約したり病院へ行くことは実際難しい、と言っていました。
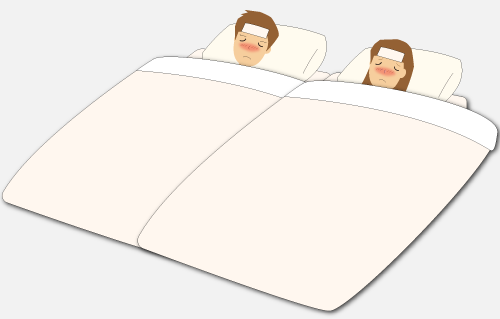
特効薬はない
風邪もインフルエンザもコロナも初期症状はほぼ同じように思います。インフルエンザの場合、抗インフルエンザ薬でウイルスを抑えることはできるようですが、どれもすぐに治る薬はないようです。
昔から風邪を治す薬はないと言われてきましたが、それで症状を緩和する対症療法がとられているわけですね。
昔から風邪予防には番茶や塩水でうがい、風邪をひくと頭を冷やして水分補給、卵酒、生姜湯、甘酒、みかん等取り入れてきました。
病院に行けずに寝込んだ友人も、最初だけ解熱剤を飲み、頭を冷やして、生姜湯やスポーツドリンクを飲んで水分補給し、1週間後には元気になったそうです。体が自力で治していると思います。
お雑煮の残りでおじや
さて、元旦は野上八幡宮への初詣が病院に、おせち料理がお雑煮の残りで作ったおじやになりました。
我が家は普段さらさらの茶粥を食べていますが、病気の時は白かいさんかおじやです。
我が家のお雑煮は、青身大根、里芋、金時人参、油揚げ、丸餅をいれ、普通の味噌に白味噌を合わせます。
青身大根(あおみだいこん)は和歌山の伝統野菜で、キュウリよりひとまわりの大きさの細い大根です。主に正月の雑煮用として使われ、年末になるとこの辺りでは店に並びます。
関西エリアで使われているようで、祝い大根、雑煮大根とも言うそうです。

野上八幡宮 えびす様へお参り
さて毎年お正月には、商売繁盛を願って、地元野上八幡宮のえびす様へお参りに行きます。
野上八幡宮は、応神天皇、神功皇后、玉依姫命を祀った由緒ある神社です。朱塗の鮮やかな本殿や入母屋造りの拝殿などは、国の重要文化財に指定されています。

私のインフルエンザのせいで延期になっていましたが、11日に役員3人でお参りにいってきました。まずは野上八幡様の拝殿前でお参り。

野上八幡様にお参り後、忠魂碑(ちゅうこんひ)の横の階段を上って恵比寿神社にお参りしました。左がえびす神社、右側に祇園神社が並んでいます。

えびす様は、漁業の神、商売繁盛の神、五穀豊穣の神として有名な「七福神」のお一人です。
右手に釣り竿、左手に鯛を抱えています。
全国のえびす様を祀ってる神社では、毎年1月9日・10日・11日の3日間「恵比須祭」を開催しています。
「十日戎(とおかえびす)」、「えべっさん」とも言います。関西、西日本では親しみのある十日戎(とおかえびす)です。
野上八幡宮も、毎年1月9日・10日・11日の3日間は商売繁盛を願って、多くの参拝客が訪れます。
9日は宵戎(よいえびす)、10日が本戎(ほんえびす)、11日が残戎(のこりえびす)。ちょうど残りえびすの日でした。
縁起物に、笹、箕(み)・熊手があり、漁業の神「えびす様」と農業の神「大黒天様」がセットになっている熊手を買いました。

毎年縁起物を買った後にのし飴を頂いています。のし飴は紅と白でできた棒状の福飴で、ねじった形の棒状は延命飴とも呼ばれており、長寿の意味が込められているそうです。

えびす様と言えば
さて、えびす様を祀る神社は、日本全国に3500ほどあるそうです。その中で日本三大えびす神社とされているのが、西宮神社(兵庫県)、今宮戎神社(大阪府)、京都ゑびす神社(京都府)です。
中でも西宮神社はえびす神社の総本社。毎年テレビのニュースで報道される「福男選び」で有名です。
また、毎年「招福まぐろ」を拝殿に飾り、商売繁盛を願って参拝客がまぐろにお賽銭を貼り付けることでも知られています。
なぜまぐろなのか?調べてみました。
なぜマグロ?
西宮神社のホームページによると、昭和44年当初、神戸市東部水産物卸売協同組合などが中心となり、大漁と商売繁盛を願って魚の奉納を計画。
翌年の昭和45年から、大ぶりで形のよい本マグロ、雄雌二尾の大ダイ、を奉納しているそうです。
参拝者に見て貰うために日本人好みの大きな魚として鮪と鯛、になったそうです。まぐろだけじゃなかったんですね。
まぐろにお賽銭を貼り付ける風習についても調べてみました。
神戸新聞の記事によると、マグロが大きすぎて本殿に置けず、参拝客の手の届く拝殿に備えられたところ、いつからか参拝客がお賽銭のつもりでマグロにお賽銭を置くようになったそうです。
凍ったマグロにお賽銭を乗せても落ちないことから、お金が身につくという縁起物になっているようです。
本年も漁業にたずさわる皆さんの安全と豊漁を願って、合羽をつくります。
(参考資料)
・大正製薬 かぜお役立ちコラム 普通のかぜとインフルエンザ、新型コロナはどう違うの?
https://brand.taisho.co.jp/pabron/kaze-ken/kaze-tigai/
・ウェザーニュース 西日本では常識?商売繁盛を願う”十日戎”とは
https://weathernews.jp/s/topics/201901/080065/
・西宮神社 年中行事・祭典
https://nishinomiya-ebisu.com/event/event01.html
・神戸新聞NEXT 十日えびす、何で大マグロに硬貨を張るの? 参拝客が始め、関西一円へ
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202001/0013018236.shtml