
皆さま、こんにちは。凍えるような寒さが続いていますね。先日酒粕を頂きました。子供の頃、こんな寒い日には温かい甘酒が振舞われることがありました。近くの野上八幡神宮でも、毎年除夜の鐘が鳴る初詣で振舞ってくれます。
この酒粕。最近は美容や健康にいいと、ちょっとしたブームになっていますね。我が家では祖父が粕汁が好きでよく食べていましたし、私は酒粕を直に炙ってお砂糖をまぶしたおやつが大好きでした。どちらも美味しいだけではなく体がポカポカになったのを覚えています。
酒粕ってすごい
改めて調べてみると、酒粕には血管を拡げる働きがあり、その結果血の巡りがよくなって体が温まるという仕組みだそうです。それだけではなく、酒粕には食物繊維と似た働きをしてくれる成分が含まれていて、便秘やダイエットから美肌効果まで注目されているそうですよ。女性には嬉しいことずくめですよね。
粕汁と骨正月
酒粕と言えば粕汁。寒い冬にふうふう言いながら食べたくなる粕汁のルーツについて、調べてみました。

photolibrary
正月用に買った尾頭付きの鮭や鰤(ブリ)を年明け少しずつ食べていき、1月20日に骨も含めた魚の残った部分を使って粕汁にして食べ尽くす習わしが、関西の風習として広まっていったと言われているそうです。それで1月20日は「骨正月」、粕汁は「始末の料理」、と言われているようですよ。寒い北の地域ではなく、意外にも関西の風習だったのですね。
粕汁にはやっぱりあのお魚でしょ。
我が家は鮭の粕汁でしたが、地域によって具材も異なるようです。ざっと調べただけでも、鮭、鰤(ブリ)、塩サバ、鰆(サワラ)、キンキ、メヌケ、いろんなお魚のアラ、豚肉等、が使われていました。海に囲まれた日本ならではの、いろんな種類のお魚が使われているんですね。思わず各地で食べ比べをしてみたくなりました。

好きなお魚ランキング第一位は?
その中でも、やっぱり粕汁に一番馴染みのあるお魚は「鮭」のイメージが強いのではないでしょうか。私も鮭は最も好きなお魚のひとつです。焼いてもお刺身でも何でも美味しいですよね。気になって調べて見ると、好きな魚ランキングで堂々の第1位となっていました。ちなみに5位までを以下にご紹介。
1位「サケ」
2位「マグロ」
3位「サンマ」
4位「サバ」
5位「ブリ」
※2020年マルハニチロ調べ
スモークサーモンのルーツは“縄文時代”かも!?
何と鮭は縄文時代から食べられていたそうですよ!縄文遺跡から鮭漁の跡が発見されていたそうです。前回のブログで干物が縄文時代から食べられていたと書きましたが、きっと鮭もそのお魚のひとつだったのでしょうね。
干物だけではなく、何と燻製にしていた形跡もあるとか。子供から大人までみんな大好きスモークサーモンのルーツは縄文時代かも!?
また、鮭にゆかりのあるお寺や神社が全国各地にあるそうです。その名も「鮭神社」という神社まであるそうですよ。
鮭は遠い昔から私たち日本人に深く関わってきたお魚なんですね。ますます鮭が好きになりました。
厳しい寒さが続いています。鮭の粕汁を食べて体を温め、寒さを乗り切っていきたいと思います。皆さまもどうぞお気をつけてお過ごし下さいね。
※Yoga journal online
https://news.yahoo.co.jp/articles/5dbf345412ce120d5e9e022078d3d6a0c74a3947
※プレスリリース 酒粕を食べることで「体は温まる」か? 月桂冠総合研究所2016年10月20日、日本醸造学会大会で発表
https://kyodonewsprwire.jp/release/201610195449
※マルハニチロ ~マルハニチロ「魚食に関する調査 2020」好きな魚ランキング
https://www.maruhanichiro.co.jp/corporate/news_center/news_topics/20201007_research_gyosyoku2020.pdf
※使用画像
鮭:無料写真素材「花ざかりの森」https://forest17.com/
荒巻鮭: photolibrary https://www.photolibrary.jp
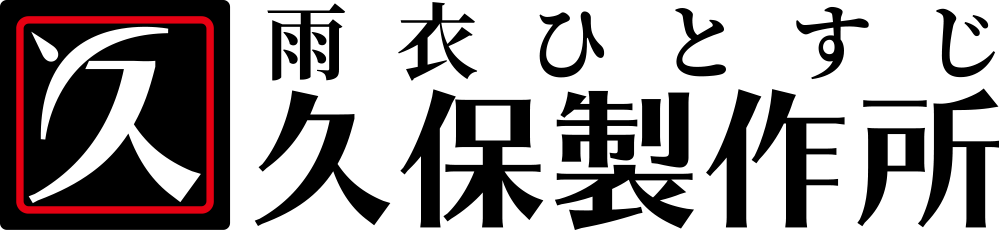











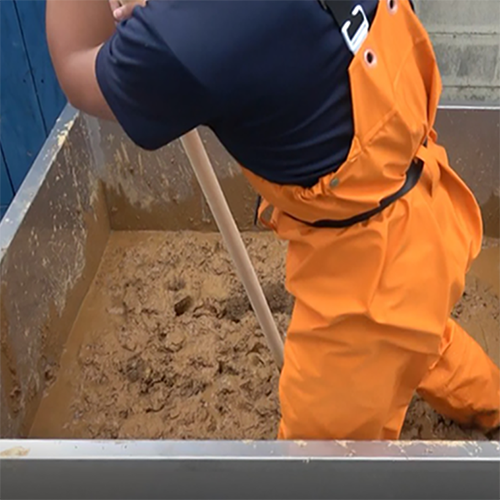


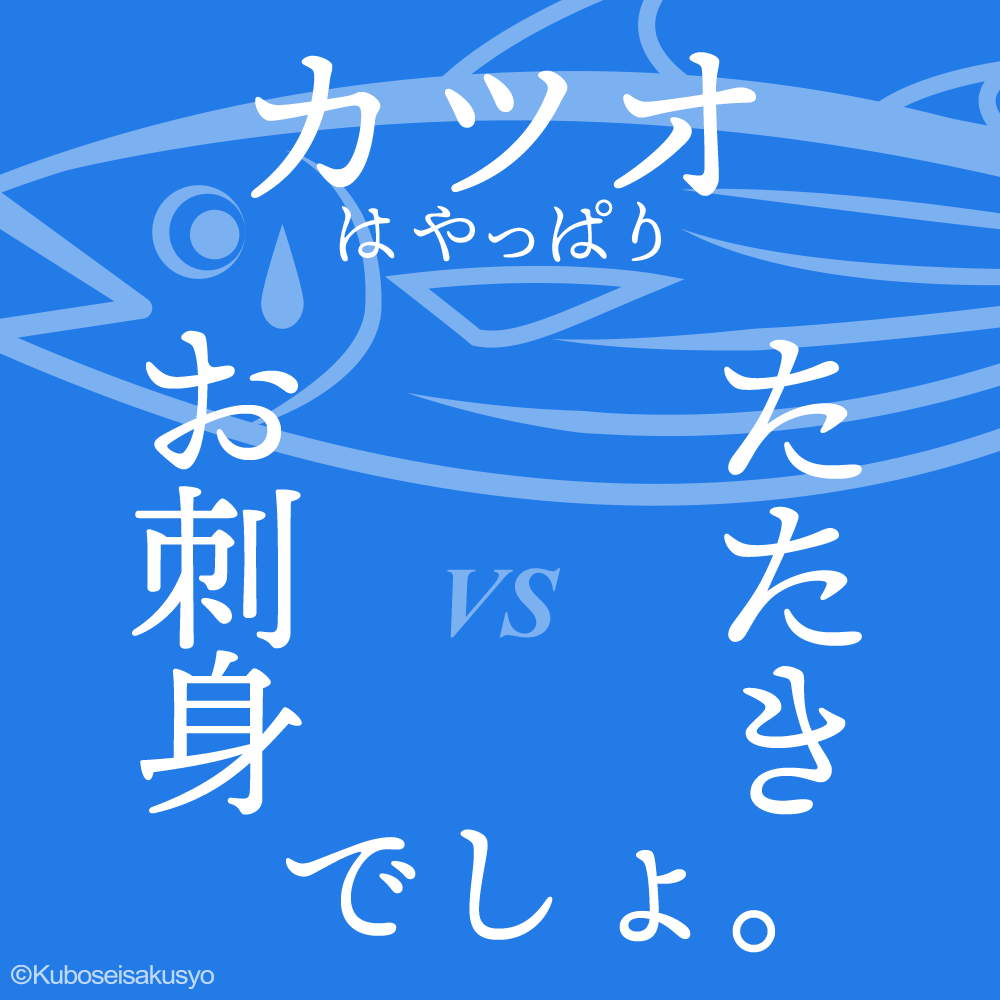

 「1社1元気技術」登録盾贈呈式
「1社1元気技術」登録盾贈呈式